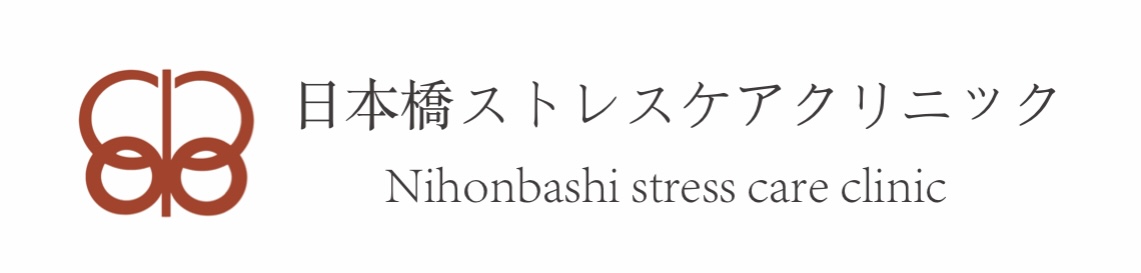漢方薬による治療法
漢方薬とは
漢方薬は、病気そのものに対する西洋医学的治療薬とは異なり、病気を持っている体質などを根本から治すことを目的として作られた薬です。病気の原因を東洋医学的に探り、悪化原因を除去するための体質改善をめざします。即効性がある場合も多いものの、長期的な改善作用のため適切なタイミングで継続して服薬すると、体質改善がいっそう進み、症状がますます軽快する伸びしろが期待されます。
「漢方医学」とは、実は中国から伝来し、日本で独自に発展体系化された医学です。中国の伝統医学を元に体系化された中医学で処方される「中薬」と、日本独自の「漢方薬」とは内容が異なり、日本人には「漢方薬」が適しているといわれてます。
西洋薬との違いは
通常、病院で処方される薬は西洋薬です。病名や症状が単一で明らかな場合は、その疾患に対して処方される西洋薬は非常に有効です。有効成分のみを分解抽出し合成作成している西洋薬は、世界的な臨床試験で多くの効果が立証された薬ですが、効果が強い反面、副作用も強くあらわれやすい特徴があります。抽出成分だけを化学合成して作られた西洋薬に対し、漢方薬は複合的な作用を有する自然生薬を原料として複数の生薬を古来から決まった比率で複雑に配合され作られ中医学では紀元前の時代より日本漢方でも平安時代までには使用がはじまり、永年にわたり安全に使用されています。身体の中の自然治癒力や免疫力を高めて、体質改善を図ることで治療していくのが主目的のため、個別の症状を抑える効果もありますが、それよりも、多種多様な症状を同時に改善することを得意とする特徴があります。体質的にこれから起きるであろうとされる起きていない症状を防ぐ効果(未病を治す)や、明確な原因が特定できない慢性疾患や自律神経失調症などの症状改善に特に有効とされています。
医療用漢方薬
■当院が処方している医療用漢方薬では、健康保険が適用されます
当院が処方している医療用漢方薬では、健康保険が適用される各社のエキス剤を用いておりますのでご安心ください。また、「ストレスケアの優しい治療法」の特徴の一つとして漢方薬での治療を行なっています。そこで、それぞれの症状に応じ適応される漢方薬についてご紹介いたします。
不眠、のどのつかえ感、不安神経症などに
■半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
疲労やストレスなどの影響により自律神経系に乱れが生じると、不安感や落ち込みなどの精神症状や、実際には何もないのに喉に何か詰まった感じがする、あるいは咳が出る、声が出にくいといった症状が現れることがあります。こうした症状を漢方では「気」の巡りが悪い状態と考えています。
半夏厚朴湯は、気の巡りを良くすることで、これらの症状を改善します。
イライラなどの神経症や肩こりが気になる人に
■加味逍遙散(かみしょうようさん)
不眠やイライラ、不安といったメンタル不調のほかに、冷えやのぼせ感、肩こり、疲れやすさなどの症状が気になる人に役立つのが加味逍遙散。婦人科三大漢方薬のひとつで、女性ホルモンの変動によってあらわれる不調に役立つ処方です。
加味逍遙散は、上がりがちな気を降ろして全身にめぐらせ、余分な熱を冷やし、不足している血(けつ)を補うことで、カラダのバランスを整える漢方薬。交感神経の興奮によるイライラや不眠症など、更年期女性の神経症状によく用いられます。また、のぼせを鎮めて血行を促進する働きも。更年期だけでなく、疲れやすい人にもおすすめです。
胃腸が弱く、ちょっとしたことで怒ってしまう人に
■抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
加味逍遙散と同じく、自律神経の乱れでイライラや不眠、緊張、怒りっぽいといった精神症状に使われる漢方薬。胃腸がやや弱いなどの虚弱体質の人におすすめの処方です。
抑肝散加陳皮半夏は、高ぶりがちな肝気を抑えることから「抑肝」という名がついています。神経を落ち着かせることで興奮や怒りを鎮め、更年期の症状を改善する効果が期待できるでしょう。更年期の不調以外にも、子どもの夜泣きや神経症、かんしゃくを和らげたいときにも役立ちます。
疲労倦怠、食欲不振、手足の冷え、貧血などに
■人参養栄湯(にんじんようえいとう)
「人参養栄湯(にんじんようえいとう)」は消化器のはたらきを高め、栄養をすみずみにいきわたらせ、「気」と「血(けつ)」の両方を補う処方です。
また、『有形の「血(けつ)」は自生することあたわず、無形の「気」より生ず』と言われるように、同時に「気」を増やすことで、補血を助ける作用があるお薬です。体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血の症状に効果的です。
血行や代謝が悪く、冷えが気になる人に
■当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
更年期の貧血や冷え、めまい、頭重感の強い人に使われることが多い漢方薬。冷えや生理不順につながりやすい「血」の不足を補い、カラダのすみずみまで栄養や熱を届ける働きが期待できます。
また、血行を良くすると同時に、水分代謝を整えることで、足腰の冷えや生理不順、気血水のめぐりを改善。更年期の精神不安だけでなく、顔が青白い、月経量が少ないといった不調にも使われることが多い処方です。
冷えを伴う生理痛、しみ、肩こり、打ち身などに
■桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
しみやアザができやすい、冷えている場所とほてっている場所がある、生理痛がつらいといった、「血」のめぐりが悪くなって起こる不調に役立つ漢方薬。血が滞ると、いわゆる「冷えのぼせ」が起き、血流の乱れによって肌にも栄養が行き届かなくなります。
桂枝茯苓丸は、血のめぐりを促すことで不調を改善。PMSや更年期のイライラを改善したり、下半身の冷えを改善したりと、血流のバランスを整えます。また、ニキビやしみなど、栄養不足で起きていた肌悩みにも効果が期待できるでしょう。
食欲不振、食後眠くなる、息切れがする、不眠などに
■補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
この漢方は疲れやすい、食欲不振、食後眠くなる、息切れがする、体力がない方の寝汗や不眠、慢性化した胃下垂、脱肛などに使用されます。過度の疲労や暑さにより消化器の機能が低下したことで引きおこる症状に対する処方です。元気のつける作用の強い黄耆や四君子湯(人参、白朮、甘草、茯苓)が含有されていて大棗、生姜、陳皮は消化機能の衰えに対して配合されています。
以上の生薬から補中益気湯は消化機能が衰えて、四肢倦怠感が著しい方に向いています。
頭痛、めまいでお困りなどに
■五苓散(ごれいさん)
頭痛、めまい、下痢などは、漢方では、「水(すい)」が滞った水滞(すいたい)を原因とする症状と考えます。
「五苓散」は、体のはたらきを高めて、余分な「水(すい)」を体の外へ出す処方のお薬。余分な「水(すい)」だけを出すので、一時的に不要な「水(すい)」が体にたまっているときに効果的な漢方薬で、口渇や尿量の減少があるような方に適している処方です。このほか、「五苓散」はさまざまな浮腫(むくみ)、急性胃腸炎、下痢、暑気あたり、吐き気にも用いられる漢方薬です。
食欲不振、胃腸虚弱、胃もたれのなどに
■六君子湯(りっくんしとう)
この漢方は四君子湯(人参、白朮、甘草、茯苓)に陳皮と半夏を加えた方剤です。
四君子湯は元気がなく、体力もないといった気虚(元気がない)という症状に使用される基本の処方で、胃腸虚弱や胃もたれに適応があります。
この、四君子湯に蠕動を促進し、食欲を促進させる人参と陳皮や、嘔吐を止め胃の浮腫を改善し、胃の機能を高める茯苓・半夏がプラスで含有されています。補中益気湯より胃の機能改善作用を高めた方剤と言えます。
不安、不眠、食欲不振、元気が出ないなどに
■加味帰脾湯(かみきひとう)
この漢方は食欲不振で元気がないなどの症候と、貧血、不安あるいは不眠などの症状が同時に見られるような場合に使用されます。
漢方ではこの症状を気血両虚と言います。帰脾湯に柴胡と山梔子という生薬が加わり、加味帰脾湯は構成されています。
帰脾湯は不安、悲壮感、不眠、食欲不振、元気がない症状に使用され、柴胡は気分を晴れ晴れとさせる効果があります。
動悸、不眠、イライラなどに
■柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
この漢方は胃腸機能を整え、抗炎症作用を有し生体を元気にする小柴胡湯に体を温めてエネルギーを巡らせる桂皮と、気分を安らかにする茯苓、精神活動を安定させる竜骨・牡蛎が加わった処方です。竜骨・牡蛎・大棗・茯苓は不安、焦燥、不眠、動悸、驚きやすさなどの症状を改善します。柴胡・半夏はイライラ、緊張、抑うつなどの症状を改善します。黄ゴン・大黄は熱を冷ます生薬で、のぼせ、火照り、怒りなどを改善します。
竜骨・牡蛎には、ふるえ、ふらつきなどを改善させる作用もあり、鎮静作用が強いのが特徴です。柴胡加竜骨牡蛎湯の特徴はこの竜骨・牡蛎が含有されていることが特徴です。以上より、本処方は動揺や驚きやすく、イライラしやすく、ストレスが原因の過興奮状態を鎮静する方剤と捉えます。
ストレスが原因の胃腸の不調に効果的な漢方薬
■半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
過敏性腸症候群などのストレスが原因の胃腸の不調に効果的な漢方薬
口から胃や腸へ飲食物が運ばれても、きちんと消化・吸収されなければ体を動かす力にはなりません。動力がなければ、今度は飲食物を消化・吸収する力も低下する、という悪循環に陥ることもあります。漢方では、この動力となるものは「気」ですが、「気」は強い圧力を受けるとその場で停滞しやすくなります。ストレスも、「気」にかかる圧力のひとつです。
「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」は、「気」が上から下に飲食物を運ぶ流れを助ける、飲食物の「気」が肺に上がっていくのを助ける、胃腸を守るという3種類の作用をもつ医薬品(漢方製剤)です。漢方で考える胃腸のはたらきに生薬が総合的にアプローチし、作用することで症状を改善していく処方です。本剤は、下痢、消化不良、吐き気、胸やけなど胃腸のはたらきが弱ったときや、口内炎などの症状に利用されます。
効能や効果としては、体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症:急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症漢方は胃腸機能を整えます。