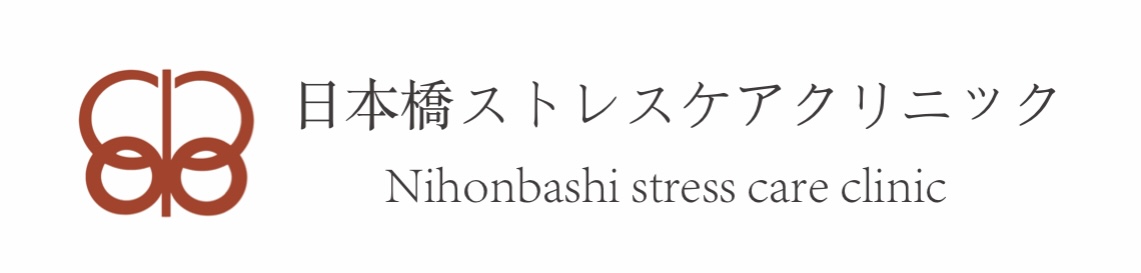うつ病・適応障害・不安障害・パニック障害
うつ病
「気分が落ち込んで、これまで楽しかったことが楽しめない」「体がだるくて、とにかく何もしたくない」「眠りが浅くて疲れがとれず、仕事や勉強が手につかない」「食欲がわかない」といった症状が続く場合、うつ病の可能性があります。しかし、治療が必要な病気なのか、それとも休んでいれば自然に良くなるのか、自分で判断することは難しいものです。多くの場合、こころの症状よりもからだの症状が気になって、まずは内科などを受診します。検査でも異常が見つからなければ、「ひとまず様子を見ましょう」と言われることが多いかと思いますが、それでも一向に良くならない場合は、早めにご相談ください。
適応障害
適応障害は、自分を取り巻く環境(仕事や家庭)にうまく馴染むことができず、そのストレスから心やからだのバランスを崩してしまう病気です。進学、就職、結婚、昇進、異動など、まわりの環境が新しくなったタイミングで発症する場合がほとんどです。ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているので、その原因から離れると、症状は次第に改善していきます。しかし、ストレス要因から離れることが難しいなど、原因を取り除くことができない状況では、症状が長引くこともありま
社会(社交)不安障害
社会不安障害は、レストランでの食事、人との会話、人前でのスピーチなど、人に注目される場面において、自分が恥ずかしい思いをするのではないかと怖くなってしまう病気です。不安な気持ちが高まるだけでなく、電車やバス、繁華街など、人が多く集まる場所を避けるようになったり、学校や仕事に行けなくなったり、日常の趣味や人間関係が制限されたりします。失敗や恥ずかしい思いがきっかけになることもよくありますが、思春期の頃は、自分に自信が持てないことがきっかけになることもあります。お薬や、考え方を修正するトレーニングを行いながら治療していきますが、治療に時間がかかることも多く、根気強く治療に向き合っていくことが大切です。
パニック障害
火事や地震など、突発的な生命の危機に直面した時、多くの人はパニック状態に陥ります。突然胸が苦しくなったり、動悸が早くなったり、冷や汗が出たりすることもあるでしょう。ところが人によって、なんでもない普通の時に、パニック状態のような反応が起きることがあります。これを「パニック発作」といいます。「この発作のせいで死んでしまうかも知れない」と不安になって、救急車で病院に運び込まれるけれども、どこを調べても異常は見つからない、といったことは、パニック障害をかかえる多くの方が経験されていることです。パニック障害では、基本的にパニック発作を何度も繰り返します。はじめは心配していた家族や友人も、次第に「またか」といった顔をするようになり、誰からも理解してもらえないつらさを感じることもあります。