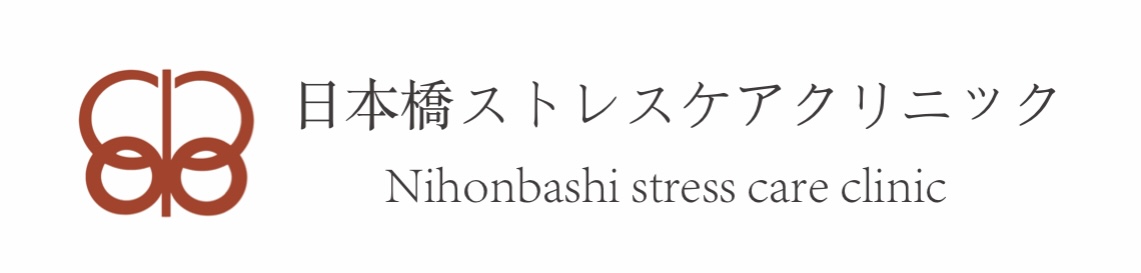発達障害・解離性障害・パーソナリティ障害
発達障害:注意欠陥多動性障害(ADHD)
注意欠陥多動性障害(ADHD)は、「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの症状を示す病気です。その程度は人によって様々で、成長とともに症状が変わっていくこともあります。
| 子ども | 大人 | |
|---|---|---|
| 不注意 | 勉強で不注意なミスが多い宿題ができない大事なものをすぐになくしてしまう興味のあることに集中し過ぎて、切り替えが苦手 | 仕事でケアレスミスが多い忘れ物、なくし物が多い時間管理が苦手仕事や作業を順序立てて行うことが苦手 |
| 多動性 | 授業中、落ち着いて座れない道路に飛び出す不適切な状況で走り回る静かに遊べない | 貧乏ゆすりなど、目的のない動きが多い会議中にそわそわ落ち着かない家事をしていても、他のことに気をとられるおしゃべりを始めると止まらない |
| 衝動性 | 質問が終わらないうちに、答えてしまう欲しいものがあると、激しく駄々をこねる授業中に不用意な発言をする | 後先を考えず、思ったことをすぐに口にする衝動買いをしてしまう衝動的に、人を傷つけることを言ってしまう |
ただ、こうした症状があるすべての方がADHDというわけではありません。似た症状をもつ病気は、他にもあります。また、ADHDに他の病気が合併していると、症状の見極めが難しくなることもあります。大人になってからADHDと診断される方の中には、子供の頃からずっとADHDの症状に悩まされていて、自分なりに工夫や対策をしていたけれども、なかなか状況が改善されずに悩んでいた、という方もいます。大学進学や就職を機に、症状が目立ってくることもあります。治療は、環境の調整を行うほか、必要に応じてお薬を使います。
発達障害:自閉症スペクトラム障害(ASD)
自閉症スペクトラム症は、「対人関係が苦手」「コミュニケーションが苦手」「特定の強いこだわりがある」といった特徴をもつ発達障害のひとつです。以前は、言葉の遅れの有無などによって「自閉症」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」などに分けられていましたが、共通した特性がみられることから、虹のように様々な色が含まれるひとつの集合体として捉えようという動きが出てきて、現在は「自閉症スペクトラム症」と呼ばれています。
| 対人関係 | 表情や話しぶり、視線などから、相手の気持ちを読み取ることができない空気を読めず、周囲の人のひんしゅくを買うことがある仕事についても融通が利かず、臨機応変に仕事がこなせない |
| コミュニケーション | 友人と親密な関係が築けない孤立する、受け持過ぎる、一方的すぎるなど、双方向の対人関係が苦手セリフを棒読みするような話し方をする |
| こだわり | 方法や順序、並べ方に強いこだわりがあり、いつも同じでないと気が済まない興味のあることは優秀な結果を出すが、興味のないことはほとんど手を付けないスケジュール管理がうまくできない |
| その他 | 些細な物音に過敏に反応するからだの動かし方が不器用である運動がぎこちなく苦手である |
このような特性のために、本人は生きづらさを感じることがあります。一方で、「人の意見に左右されず、課題を遂行できる」といった特性が、むしろその人の強みになることもあります。「高い記憶力」「好きなことへのこだわり」といった特性をうまく利用して、仕事や趣味で充実した生活を送っている方もいます。その人が持って生まれた「個性」ととらえて、生きづらさを軽減しながら、得意なことを伸ばすサポートが大切です。
発達障害:学習障害(LD)
学習症の子どもに対しては、教育的な支援が重要になります。読むことが困難な場合は大きな文字で書かれた文章を指でなぞりながら読んだり、文章を分かち書きにしたり文節に分けることも有用です。音声教材(電子教科書)を利用することも可能です。書くことが困難な場合は大きなマス目のノートを使ったり、ICT機器を活用したりすることも可能です。計算が困難な場合は絵を使って視覚化するなどのそれぞれに応じた工夫が必要です。学習症は、気づかれにくい障害でもあります。子どもにある困難さを正確に把握し、決して子どもの怠慢さのせいにしないで、適切な支援の方法について情報を共有することが大事です。
解離性障害
解離性障害は「自分が自分である」という感覚を失ってしまう状態のことです。たとえば、過去の記憶の一部が抜けて落ちていたり、体の感覚の一部を感じられなくなったり、感情が麻痺したり、いつのまにか自分の知らない場所にいたりします。原因としては、災害、事故、虐待、暴行、レイプなどによるストレスや心的外傷が関係していると言われています。解離性障害でみられる症状は、つらい体験から自分を切り離そうとするために起こる、一種の防衛反応です。治療の基本は、安心できる環境をつくること、家族などまわりの人に病気を理解してもらうこと、主治医との信頼関係をつくることなど、安心できる関係性を築くことです。
パーソナリティ障害:境界性パーソナリティ障害
境界性パーソナリティ障害(borderline personality disorder)とは
境界性パーソナリティー障害は、出現率が約2~5%程度であると考えられており、男女比はそれほど違いがありません。
病院受診している患者さんには女性の割合が多くなっています。
青年期から成人期の初め頃にははっきりと傾向が現れるようになります。
対人関係、自己像、感情、行動が不安定で、計画性のない悪い結果に繋がる犯罪などを引き起こしてしまうような衝動性がみられます。
年齢を重ねるとともに症状は見られなくなりますが、対人関係や社会性においてはそれほど改善しないことが特徴です。
境界性パーソナリティ障害の症状
見捨てられている、誰も気にかけてくれない、といったことに対して極端に敏感になってしまいます。
ただし、見捨てられることは現実に起こっているとは限らず、そのような状況になるのを避けようとして怒りや絶望、抑うつ、自暴自棄などといった感情に支配されてしまいます。
その結果として自傷行為やOD(薬物の過剰に摂取)、過食、飲酒、自殺企図などが見られるようになりますが、さらに人間関係を不安定にするきっかけとなり悪循環に陥ってしまいます。
できる限り、人間関係を深く持たないようにする人もいます。
境界性パーソナリティ障害のチェックリスト
境界性パーソナリティー障害は、上記でお伝えした米国精神医学会の診断基準である「DSM-5」が日本でも使われることになります。
下記の9つの項目のうち5つ以上に当てはまっている場合には、境界性パーソナリティ障害であると診断されることになります。
- 人から見捨てられること(現実に起こっているとは限らず)を避けようとしてなりふり構わず必死に行動している
- 人間関係は不安定で激しいのが特徴で,相手を理想だと思ったり幻滅したりといった評価が揺れ動いている
- 不安定で曖昧な自己像(アイデンティティー)や自己意識、自己観を常に持っている
- 衝動的に自分に害を及ぼすような安全ではない性行為や過食、向こう見ずな運転などといった行動を取ってしまう
- 何度も自殺しようとしたり、自分の手首を傷つけるような自傷行為をしてしまう
- 突然怒りを爆発させたり、落ち込んでしまうことがあるが数時間でおさまることが多く,数日以上続くことはあまりない
- 何をしていても虚しく感じてしまう
- 自分の思い通りに行かないと強い怒りの感情を持ってしまい、怒りをコントロールすることができない
- ストレスを強く感じてしまうことによって一時的に妄想のように感じてしまうことがある
パーソナリティ障害:回避性パーソナリティ障害
回避性パーソナリティ障害とは
回避性パーソナリティ障害は、他人との関わり合いに対する深い不安、劣等感、社交の場面での緊張などが特徴的な精神障害です。人と親しくなることを望みながらも、拒絶や批判される恐れから関係を避ける傾向があります。この状態は、個人の社会生活や職場での機能に大きな支障を来たし、日常生活においても様々な制限をもたらすことがあります。
1、概要と症状の特徴
回避性パーソナリティ障害を抱える人々は、他人に対する批判や嫌悪を強く恐れるため、新しい人間関係の構築を極度に避ける傾向にあります。また、退けられることへの恐怖が、人前での自己表現を避ける行動につながります。症状には社会的抑制、劣等感、過敏な拒絶恐怖、自己評価の低さが含まれ、総じて社交的な状況を避ける傾向が見られます。
2、回避性パーソナリティ障害の生起背景
発症には多数の要因が関与しており、遺伝的な素因や幼少期の経験、特に親子間の関係性などの環境的要因が絡み合っているとされています。生い立ちにおける交流の欠如や過保護など、社会的スキルが培われにくい環境が、症状の発達に寄与すると考えられています。
2 疫学的頻度と性差
回避性パーソナリティ障害の疫学的頻度は、地域や調査方法によって異なるとされていますが、国際的な精神疾患の分類であるDSM-5によると、一般人口における有病率は約2.4%と推定されています。特に、日本においては、精密な疫学調査が求められており、国内の具体的な発症率は明らかになっていない側面もありますが、臨床経験に基づく報告によれば、心理的な支援を求める個人の中でこの障害が見られる頻度は高いとされています。
(1) 日本における発症率
日本での回避性パーソナリティ障害の発症率に関する公的な統計は少ないものの、専門家による小規模な研究や臨床報告が行われています。こうした研究では、他の社会不安障害やうつ病との共存が指摘されることが多く、日本特有の社会構造や文化的要因が影響している可能性が考えられます。
(2) 性別による発症の違い
性別に関しては、一般に男女差が少ないとされることが多いのですが、一部の報告によると女性の方が診断される頻度がやや高いことが示唆されています。この性差は社会的な期待や役割に基づくストレス、求められるコミュニケーションの仕方の違い等によると考えられ、男性と女性で発症や症状の現れ方に差が出ることがあります。
| 性別 | 推定有病率 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 男性 | やや低め | 社会的期待の差異、リーダーシップを求められるケースなどによる影響が考えられる |
| 女性 | やや高め | 対人関係におけるストレスや、性別に根ざした役割期待に起因する可能性 |