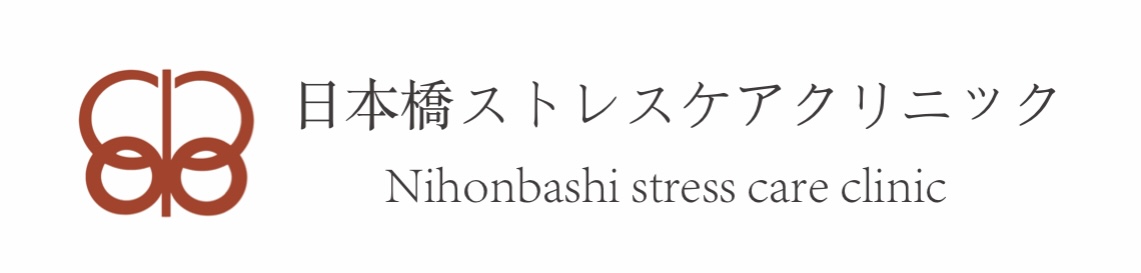バイタルチェックについて
バイタルサイン
バイタルは「バイタルサイン」の略称です。バイタルサインは英語で「vital signs」。日本語で「生命兆候」と訳されます。
生命兆候とは、人間が「生きている」 ことを示す指標のことです。「脈拍」「血圧」「呼吸」「体温」の4つを指標とし、数値を測定することでその日の健康状態を知ることができます。そして、数値の経過をみることで、体がどのような状態か判断することが可能となります。
ポイント
普段から体温計や血圧計を使って測定結果を記録しておくと、自分の平均的な体温や血圧を知ることができます。また、普段の状態を知っておくことで、自分の体の変化に気づきやすくなります。
脈拍
脈拍は、一定の時間に心臓が拍動する回数のことを表しており、通常は1分間の拍動を数えます。一般的に手首の親指側、動脈が触れる場所で測定するので「脈拍」と言われます。 自動血圧計で血圧を測定すると、血圧の数値の高い値と低い値、そして「脈拍」の数値が出てきます。
脈拍を知ることで何がわかる?
脈拍は、身体のすみずみまで血液が行き渡っているかどうかを知る指標になります。脈拍の数やリズムに異常があると、心臓や血液循環に関連した病気が疑われます。また、リハビリやスポーツを行う時の運動強度の指標にも用いられます。
脈拍の正常値は1分間に60〜100回。個人差が大きく、年齢や体温、動いたあとなどの活動内容によっても、容易に数値が上下します。医療従事者は、脈の触れる部位の拍動の大きさやリズムも感じながら脈拍を測定しています。
不整脈とは
動悸(どうき)や胸痛を感じたときに脈を触れてみると、不規則なリズムの脈拍や、脈が飛んでいるような触れ方をするときがあります。自覚症状がない場合もありますが、気になる方は医療機関で一度相談してみてください。
さまざまな種類が存在する不整脈。なかには突然死の原因となる場合もありますが、持病として不整脈がない人でも、体調不良時に不整脈を起こしていることはよくあります。生まれつきの不整脈や、息を吸うと脈拍が増える方もおられ、様子を見てよい場合もあります。
血圧
「年齢とともに血圧があがってきた」そのような方も多いのではないでしょうか。血圧とは、心臓から全身に送り出される血液が血管の壁を押す力のことで、心臓が筋肉をギュッとしぼめた時を上の血圧(収縮期血圧・最高血圧)、逆に筋肉が最もゆるんだ時を下の血圧(拡張期血圧・最低血圧)といいます。
血圧を測ることで何がわかる?
血圧を測ることで、心臓から出た血液がどれだけの力で血管の壁を押しているかがわかります。この壁を押す力が強いと、年齢と共に硬くなっている血管の壁を傷つけてしまう恐れがあります。その傷は脳卒中や心臓病の引き金ともなりやすいので、高血圧には特に注意が必要です。
高血圧ってどれくらい?
日本高血圧学会では、正常血圧は上の血圧が120mmHg、下の血圧が80mmHg未満と規定しています。細かい分類はいくつかあるのですが、一般的には上の血圧が140mmHg以上、下の血圧が90mmHg以上の場合が高血圧状態といわれています。
※mmHg(ミリメートルエイチジー)は血圧の単位です
ポイント
血圧が高いと言っても、運動直後や受診の時に測る場合は高くなることが多いです。「血圧が高いかも……」と思って測ると高い時もあります。普段から測っていると「いつもの血圧の上がり方と違う」と気が付くことがあります。病気の早期発見のためにも普段から血圧を測ることを心がけましょう。
呼吸
生物が身体を動かすエネルギーを作るために必要な要素の1つに酸素があります。この酸素を肺で体内に取り込み、細胞で消費し、老廃物となる二酸化炭素を体外へと排出する仕組みが「呼吸」と言われています。 バイタルサインの中でも「呼吸」は「みて」「きく」 ことによってわかることが多くあります。
呼吸の数え方
呼吸の回数を測るときは、相手に測ることを意識させずにリラックスした状態で測ることが大切となります。「吸って吐く」を1回と数え、胸やお腹の動きをみながら1分間測定します。成人の場合、1分間に12~20回の数が正常値とされています。
正常値は年齢によって異なり、新生児では35~50回、乳幼児は30~40回と言われています。これは新生児から学童期に至るまでの間は肺の成長途中であり、1回で換気できる量が少ないため、呼吸の数で取り込む酸素の量を補っているからです。
正常呼吸とは
安静時に、1分間の呼吸が30回を超えていたり、「ヒューヒュー」と異音が鳴っていたり、呼吸のリズムが一定でなかったりと、いつもと呼吸パターンが極端に違う場合はいろいろな病気が関連していることが考えられます。
唇の色が青紫色になるチアノーゼは、血液中の酸素濃度が低下した際に現れるサインなので特に注意が必要です。異常を見極めるには普段からの呼吸の回数・深さ・リズム・呼吸音を知り、異常が現れた際には何が原因か探っていくことが大切です。
体温
「調子が悪いかな?」そう思ったときには、まず体温を測る、という方も多いと思います。ヒトは、 環境が変わって気温が変化しても、体温も同じように変化することはなく、ある程度は維持することができます。その体温が変化していくと、体の中で何らかの異常が起きている場合があります。
体温を測ることで何がわかる?
熱が高いときは、体のどこかに感染症がある場合が多く、その他には身体内の出血や、がんのような疾患によって上昇することもあります。熱が低いときの原因としては、寒い場所に長時間いる場合やお酒の飲みすぎ、 栄養低下などが考えられます。
平熱ってどれくらい?
一般的には、36℃〜37℃とされていますが、個人差があり、体温を測定する時間や食事・運動などの活動、性別、年齢によっても変動します。36〜37℃が、身体の中の細胞を効率的に働かせる温度と言われています。
ポイント
気温が高いときや、布団、着衣が体の熱を逃がしにくくしている場合に、体温が上昇してきます。こうした状態を「こもり熱」といい、「こもり熱」がひどくなってくると、真冬でも熱中症の状態となってしまいます。体位を変えたり、衣服や掛布団を調整することで「こもり熱」 を予防することができます。